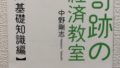奇跡の経済教室〜基礎知識編〜
中野剛志著
本書は経済学者や官僚でも知らないような高度な内容を、だれでも理解できるように分かりやすく経済学について説明したものになります。
内容としては、一部と二部に分かれていて、一部は、「おカネとは何か」、「税とは何か」といった根本的な問題にまで掘り下げて解説したものになり、二部では、著名な経済学者たちの議論を批判的に検討してみるという内容になります。
この記事では、一部の「おカネとは何か」、「税とは何か」についてご紹介したいと思います!!
規制緩和、自由化、グローバル化、消費増税全てデフレ下において逆行していることがわかり、目からウロコが落ちること間違いなしです!
二部の著名な経済学者たちの議論を批判的に検討してみるという内容の記事についても是非ご覧ください!
|
|
〈本書の15のポイント〉
1.平成の日本経済が成長しなくなった最大の理由は、デフレである。
2.デフレとは、需要不足/供給過剰が持続する状態である。
3.新自由主義は、本来インフレ対策のイデオロギーである。
4.平成日本は、デフレ下にあったのに新自由主義のイデオロギーを信じてインフレ対策をやり続けた。
5.貨幣とは、負債の特殊な形式である。(信用貨幣論)
6.貨幣には、現金通貨と預金通貨がある。
7.現代貨幣理論の貨幣理解が重要である。
8.量的緩和では、貨幣供給量は増えない。
9.財政に対する正しい理解が重要である。(機能的財政論)
10.財政赤字を拡大しても、それだけでは金利は上昇しない。
11.国内民間部門の収支+国内政府部門の収支+海外部門の収支=0
12.税収=税率✖️国民所得
13.財政健全化ではなく、経済健全化を目指さなければならない。
14.自由貿易が経済成長をもたらすとは限らず、保護貿易が経済成長をもたらすこともある。
15.主流派経済学は過去30年間で、退歩した。
・日本経済が成長しなくなった単純な理由
・デフレの中心で、インフレ対策を叫ぶ
・経済政策をビジネス・センスで語るな
・仮想通貨とは、何なのか?
・お金について正しく理解する
・金融と財政をめぐる勘違い
・税金は何のためにある?
・日本の財政破綻シナリオ
・日本の財政再建シナリオ
・感想
●日本経済が成長しなくなった単純な理由
・1998年以降20年以上の日本のデフレは、戦後の世界では他に類を見ない。日本経済が成長しなくなったのは、明らかに政府の経済運営の誤りが理由である。
・デフレになると、消費と投資は減り、需要はさらに縮小するので悪循環から抜け出せなくなる。デフレはお金の価値の上昇であり、そうなるとモノよりもお金を大事にするようになり経済が回らなくなる。
・日本の経済成長の衰退の最大の原因はデフレである。経済成長は、基本的にはインフレを前提としている。しかし、ハイパーインフレになるとお金はただの紙切れになってしまう。そのためちょうどいい塩梅のインフレの維持を目指した経済の舵取りが理想である。
・しかし、国内に競争相手のいない製品やサービスの輸入価格が上がることは、インフレを起こすが、これは企業や家計を圧迫する景気を悪化させる方向にしか働かないインフレである。
デフレも同様に国内産業を保護した輸入関税が引き下げられる場合は、国内産業は需要を失ってしまう。
・「合成の誤謬」この言葉がキーワード。景気が悪い時は支出を切り詰めなければ、個人や企業は生き残れない。不景気な時に節約して貯蓄するのは美徳ですらある。しかし、個人や企業が支出を減らせば需要が縮小して景気はますます悪化する。このように個々の正しい行動でも積み重なると全体として好ましくない結果となることを合成の誤謬と言う。そのため、デフレ下こそ政府の存在意義が重要になる。
●デフレの中心で、インフレ対策を叫ぶ
・企業が内部留保を貯め込むのも、賃上げしないのも、積極的な投資をしないのもひとえに、デフレという経済環境のせいである。
・経済政策というのは、経済全体の環境を調節すること。デフレを解消出来るのは、経済政策を発動して、経済全体を調節出来る政府だけである。
・インフレ対策には、政府が支出を削減し、増税する、また日銀の金利引き上げなどを行うことで需要を抑制する。また、規制緩和や自由化によって供給力を上げる。いわゆるグローバル化をする。
・デフレ対策には、政府は社会保障や公共投資を拡大して支出を増やす必要がある。また、減税を行う、消費税は減税し、企業に対しても投資減税を行う。政府が財政支出し、減税を行うということは財政赤字を拡大するということである。そして日銀は金融緩和をすること。また、供給力を下げるために、規制緩和や自由化は行わない方がよい。グローバル化を抑える。
・サッチャーやレーガンが新自由主義に基づく政策を実施したのは、当時のイギリス、アメリカがインフレだったからである。また、デフレ対策として有名なのは世界恐慌時のルーズベルトが実施したニューディール政策である。
・ところが、平成日本は、デフレ対策が求められる中、構造改革と称するインフレ対策を20年以上実行してきた。平成日本は、サッチャーやレーガンが実施した新自由主義が席巻した時代である。昭和日本は一種の社会主義であり、冷戦終結により新自由主義へと改革してきたが新自由主義はあくまでインフレ対策のイデオロギーである。
●経済政策をビジネス・センスで語るな
・改めてデフレとは、需要不足/供給過剰の状態である。そんな時に、生産性を向上させればどんどんデフレが悪化する。一企業の立場であれば、生産性向上や競争力を強めることは良いこと。しかし、全企業がそうなると経済全体としては好ましくない結果をもたらす。
・生産性の向上が経済全体にとって好ましいのは、インフレの時だけである。政府は、まずはデフレ脱却を果たし、経済をインフレにしてその上で生産性の向上を促し、経済成長を実現すべきである。
・企業間の競争を促進して、競争に負けた企業は潰してしまう。平成の構造改革の時代にゾンビ企業なんか淘汰されればいい。と言った意見が蔓延していた。しかし、競争によって企業を淘汰すると供給だけでなく、需要も削減されるため結局需要と供給の差は変わらずデフレは解消しない。
・「非効率な企業が淘汰されれば、経済は成長する」今だに根強いこの主張は、”国の経済運営のやり方と、企業経営のやり方を混同しているため”である。一企業の場合、無駄な部門の排除や企業の外に追い出すことは可能だが、経済全体となると企業を潰すと従業員は経済から消えず失業者としてとどまる。こうして遊休資産が増え、経済は非効率になるのである。
・デフレ時には大きな政府が望ましい。政府が支出を増やせば、需要が生まれる。従業員の給料を上げれば、所得が増え、消費も増えるため、デフレ対策として有効なのである。消費を増やすには所得を増やす必要がある。
・最善の策は必要なものを造る公共投資、次善の策は無駄なものを造る公共投資、無策は公共投資を増やさないこと、最悪の策は公共投資の削減である。平成日本は、無策と最悪の策ばかりだった。バブル崩壊後、「巨額の公共投資が景気対策として行われたが、不況から脱せなかった。」との主張は間違いである。なぜなら日本経済がデフレに突入したのは、公共投資が減少し、消費税を5%に上げた1998年以降だからである。90年代前半の公共投資の増加も一般政府が13兆円、中央政府が1.5兆円と大した増加ではなかった。むしろ多すぎたのではなく少なすぎたのである。
・国際通貨基金IMFも、当時の90年代日本の財政政策について規模は不十分だったものの、効果がなかったのは間違いだとしている。経済として一般的にデフレは異常であり、マイルドなインフレが正常である。正常に成長している経済では、物価は穏やかに成長するからである。デフレが長引いている理由の1つは、政府がデフレ対策を理解するのが難しいからだろう。
●仮想通貨とは、何なのか?
・平成日本の経済学者の中には、「デフレとは貨幣の価値が上がる現象だ。デフレから脱却するには、貨幣の価値を下げ、そのためには貨幣の供給量を増やしさえすればよい。」と主張する人もいた。貨幣の供給量はどうすれば増えるのか。そのためには貨幣とは何かを理解する必要がある。
・現在世間を賑わせている仮想通貨を題材にして、貨幣は何かを考えることが重要である。2018年時点で、仮想通貨を世界で最も多く保有しているのは日本人である。ビットコインは昔の金や銀と同じように鉱山採掘に該当するマイニング(採掘)と呼ばれる数理処理が必要であり、まさに金銀貨幣の電子版である。
・ビットコインについては、竹中平蔵氏、アップルのウォズニアック氏、哲学者東浩紀氏が絶賛している。3方の共通見解として、「仮想通貨は、政府や中央銀行のような中央集権的な権力から自由な通貨である」という点を高く評価している。しかし、仮想通貨の決定的な欠点として、供給量の制限があり、制限があることで需要が増えると貨幣の価値が上がりデフレを引き起こすことになる。
・仮想通貨は、貨幣の供給量は金の量に制約されていた金本位制の時代に起きた世界恐慌を起こすことになりかねない。ビットコインの仕組みは、金本位制という古くて欠陥のある制度と発想が同じである。これに対して、現代通貨は不換通貨であり、デフレを回避出来る。東浩紀氏は、中央銀行のような権力に頼らずに誰でも発行出来ると称賛しているが、誰でも発行出来る通貨など誰も欲しがらず、デフレとは反対のハイパーインフレを引き起こしかねない。
つまり、ビットコインは金本位制の時のような供給制限があることによるデフレや誰でも発行出来ることによるハイパーインフレを起こしかねないのである。
●お金について正しく理解する
・イングランド銀行の季刊誌に掲載された「貨幣とは負債の一形式であり、経済において交換手段として受け入れられた特殊な負債である。」いわゆる信用貨幣論である。
この信用貨幣論と金本位制や仮想通貨に基づいた商品貨幣論どちらが正しいのか。
・結論は、信用貨幣論が正しくて、商品貨幣論は間違いである。紀元前3500年頃のメソポタミアにおいては、官僚たちが、臣下や従属民から必需品や労働力を徴収し、彼らに財を再分配しており、債権債務を計算したり、記録したりするための計算単位として貨幣が使われていた。また、古代エジプトは私有財産や市場における交換は存在しない世界だったが、貨幣は存在しており、国家が税の徴収や支払いなどを計算するための単位として使われていた。
・デフォルト(債務不履行)の可能性がほとんどないと信頼される特殊な負債のみが、貨幣として受け入れられ、流通する。中央銀行券と鋳貨と預金通貨が、その特殊な負債にあたる。
・銀行は貸出しによって、預金という貨幣が創造される。そして、借り手が債務を銀行に返済すると預金通貨は消滅する。日本の全国銀行協会が編集している図説にも「銀行が貸出しを行う際は、貸出し先企業Xに現金を交付するのではなく、Xの預金口座に貸出金相当額を入金記帳する。銀行の貸出しの段階で預金は想像される仕組みである。」とある。
・銀行の貸出しが元手となる資金の量的な制約を受けることはない。もし、銀行が元手となる資金を集めなければ貸出しが出来ないのだとしたら巨額の設備投資は不可能になり、現代の資本主義は成り立たない。イギリスの産業革命においても先行して銀行制度があったからだと言われている。つまり、資本主義が発展し続けてきたのは信用創造という恐るべき機能を持つ銀行制度があったからである。
・銀行の貸出しの制約があるのは、貸手の方ではなく、借手の返済能力である。具体的には、リーマンショックは、リーマン・ブラザーズ・ホールディングスが借手の返済能力を鑑みずに貸し続けた末路と言える。もう1つの制約は、いざという時の現金通貨引き出しに備えて日銀に一定額の準備預金を設けなければならず、この準備預金制度も銀行の貸出しの制約となる。
・銀行が貸付によって預金を創出出来るのであれば、なぜ銀行は個人や企業からの預金集めに奔走するのか?それは、銀行は貸付によってお金を生み出すが、そのお金は他行に流出することが多いからであり、流出した資金の”穴埋め”をするために預金集めに奔走するのである。自行の資金繰りを円滑にするためである。
・通貨は納税の手段となることで、その価値を担保している。この説を採用する経済理論をMMT(現代貨幣理論)と呼ぶ。現代貨幣理論は、通貨の価値を裏付けるものは租税を徴収する国家権力であると唱えている。現代貨幣理論が主張したいのは、国家が納税手段として、法的したものは、全て貨幣として使われるということ。実際に、現代の通貨はその価値を国家の徴税権力に裏付けられている。
一方、仮想通貨では、納税義務の解消は出来ず、仮想通貨の価値を支える基盤的な価値は何もない。
●金融と財政をめぐる勘違い
・貨幣とは現金貨幣と預金貨幣があり、預金貨幣が8割を占める。銀行は、借り手の預金口座に金額を記帳するだけで、金額の預金を生み出すことが出来る。
・中央銀行は、マネタリーベース(現金通貨と準備預金の合計)の量を操作することで、貨幣供給の量を操作出来る。しかし、借り手のほうに資金需要がない限り、銀行の貸出しは増えない。今まで述べたように、借り手の資金需要が貸出しの制約になっているのでデフレの時には、中央銀行は貨幣供給量を増やせず、インフレを起こせない。マネタリーベースを増やしたところで貨幣供給量は増えないのである。
・財政危機であれば国債を買う人がいなくなるので、金利は暴騰するはずである。しかし、日本国債の金利は世界最低水準で推移し、政府債務が積み上がっているのに金利は逆に下がっていった。日本は財政危機なのに、日本国債の買い手が山ほどいるのである。
・銀行は、日銀に儲けられた日銀当座預金を通じて、国債を購入している。集めた民間預金を元手にして購入しているわけではない。では、日銀当座預金はもとはといえば、日銀が供給したものである。すなわち銀行による国債購入は、日銀が政府から直接国債を購入して当座預金を供給する「財政ファイナンス」とほぼ同じである。
財政ファイナンスは、ハイパーインフレになるから絶対やってはいけないことになっているが、銀行の国債購入という事実上の財政ファイナンスは普通に行われており、しかしながらハイパーインフレになっていない。民間貯蓄が財政赤字をファイナンスしているのではなく、財政赤字が民間貯蓄を生み出しているのである。
・政府が国債を発行して財政支出を行なった結果、支出と同額の民間預金が新たに生まれている。つまり、政府の財政赤字支出は、民間貯蓄を減らすのではなく逆に増やすのである。財政赤字の増大により、民間資金が不足し、金利が上昇するということはありえない。
・貨幣供給量の増大に必要なのは、財政赤字の拡大である。政府が負債(貨幣)を増やせば、貨幣供給量は増えるのである。そして貨幣がきちんと消費や実物投資の方へと流れるように産業構造を構築する政策が必要になる。いくら金利の引き下げやマネタリーベースの増加によって、銀行の貸出しを容易にしたところで、借り手の需要がない以上、銀行は貸出しを行うことは出来ない。
・日本は、デフレ化に大規模な異次元緩和、消費増税などの財政再建、民営化などの構造改革、グローバル化を進めてきた。デフレ脱却と経済成長を望んできたが、これは国民、経済学者や経済官僚の多くが貨幣について正しく理解していないということになる。そして日本人は、仮想通貨を世界で最も多く保有している国民である。デフレから脱却出来ないことと、仮想通貨に飛びついていること。共通するのは、貨幣に対する正しい理解の欠如である。
●税金は何のためにある?
・政府の返済能力の限界はどこにあるのか。日本政府についていえば、その返済能力には、限界はない。なぜなら、借金の返済に必要な通貨を発行しているのは、他ならぬ政府自身だからである。政府は通貨を発行する能力があるという点において、個人や民間企業とは決定的に異なる。自国通貨建ての国債は、返済不能に陥ることはあり得ない。歴史上、他国でもそのような例はない。アルゼンチンなどは外貨建て国債についての債務不履行であった。ギリシャやイタリアが財政危機に陥ったのもユーロ建てだったからである。
・国債の償還の財源は税である必要はない。新規に国債を発行して、それで同額の国債の償還を行う借り換えを永久に続ければよいのである。実際ほとんどの先進国では、国家予算に計上する国債費は利払い費のみで償還費を含めていない。日本政府はなぜか償還費も含めている。
・では、財政赤字の限界は何か。当然ハイパーインフレになれば通貨はただの紙切れになってしまう。であれば、財政赤字の制約を決めるのはインフレ率(物価上昇率)である。無税国家にすると、やがてはハイパーインフレになってしまうため、税金は必要である。財政が経済においてどのように機能しているかこの考え方を機能的財政論という。
・財政赤字の制約となるのは、民間部門の貯蓄でもなく、政府の返済能力でもなくインフレ率である。財政赤字が多すぎるのであれば、インフレが行き過ぎているはずであるが、日本はデフレである。財政赤字は多すぎるのではなく、少なすぎるのである。19世紀前半のイギリスは累積政府債務が国民総生産の300%に達していたが、ハイパーインフレにも財政破綻にもなっておらず、大英帝国として謳歌していた。
・税金の必要性は、インフレが行き過ぎるのを防ぐためである。税金は物価調整の手段であり、財源確保の手段ではない(自国通貨建てが出来る国のため)。政府が消費増税を正当化する理由は、財源確保である。しかし、税は財源を確保する手段ではなく、物価調整の手段である。デフレ下の日本で必要なのは、投資減税、消費減税といった手段によって、物価を上げることである。
・税には、物価調整以外の目的のためにも活用される。例えば、炭素税による二酸化炭素排出抑制。また富裕層の所得や贅沢品の消費の課税を重くすることで所得格差の是正が出来る。消費に回す割合が高い低所得者にお金を回す方が消費需要は拡大する。つまり格差の是正は、需要の拡大を通じて、経済成長を促すのである。逆に格差が拡大すると、需要は減少し、経済成長は阻害される。平等な社会は、競争原理が働かず経済が成長しないというのは嘘である。消費増税は格差の拡大を引き起こし、経済成長を鈍化させる。
・税収を確保したい財務健全化論者にとっては、不景気になると税収が激減する所得税や法人税よりも、確実に徴収出来る消費税の方がいいのである。税収が増えるということは、負債である貨幣が消滅し、貨幣供給量が減るのでデフレが悪化する。日本の平成の税制を振り返ると、デフレ下であるにも関わらず、所得税の累進度を弱め、法人税を下げ、消費税をあげたのである。企業の内部留保が増えているのは、経営者が無能だからではなく、政府が無能だからである。
●日本の財政破綻シナリオ
・デフレを脱却し、インフレ率が2〜4%になる程度まで、財政赤字を拡大する。ハイパーインフレを恐れる必要はない。財政赤字の拡大を止められないと言うハイパーインフレ論者に対しては、景気が良くなればつまり、インフレになれば税収が自然と増えるので、財政赤字は減らせるのである。そもそもハイパーインフレが起きた例は、第一次世界大戦後のドイツや1990年代の旧ソ連や独裁政権下のジンバブエなどのレアケースのみである。
・2012年、財政危機に陥ったギリシャでは、長期金利が40%を上回っていた。財政赤字の拡大が金利の上昇を招くと心配する論者はこれを恐れている。しかし、日本の金利は0.03%程度であり、日本国債は買われ続けて、引くてあまたなのである。その理由の1つがデフレだからである。金融機関は国債を買うしかないためである。2つ目が市場は、日本の財政が破綻するなどとは信じていないということである。金利が上がらないのは、市場は日本円が安全資産であること、つまり日本の財政破綻などあり得ないと分かっている。そして3つ目が日銀による大量国債購入である。日銀が国債を買うので、国債が買い手を失って金利が高騰することは考えられないのである。仮にもし、金利が急騰しても、国債の買い手はすぐにつくので、金利はたちまち下落する。それでも、下がらなければ日銀が国債を購入すれば、金利は下落する。
・一般の財政破綻の定義は①政府が債務不履行に陥ること②ハイパーインフレになること③金利が急騰することである。
①の債務不履行になるには、日本政府は必要もないのに外貨建てで国債を発行すると決め、固定為替相場制にして経常収支が赤字になるまで財政支出を拡大し続ける必要がある。
②のハイパーインフレになるには、まず無税国家にして、財政支出を拡大し続ければ、ハイパーインフレが起きるのである。
③の金利高騰シナリオは、デフレ下にもかかわらず国債の金利を高騰させるには、日本の財政破綻宣言をして市場を信じ込ませるしかない。
いずれにしても、国家に財政破綻したいという狂気に満ちた政治的な意志がなければ起こりえない。
●日本の財政再建シナリオ
・プライマリーバランスとは、その時点で必要とされる政策的経費を、その時点の税収等でどれだけまかなえているかを示す指標とされている。プライマリーバランスの目標は、2002年、小泉内閣の下で設定された。2007年には2012年にプライマリーバランスの黒字化の達成をする目標が設定されている。
・アルゼンチンは、1990年代初頭に経済危機に陥り、IMF(国際通貨基金)に救済を依頼したところ、融資の条件として2003年にプライマリーバランスの目標達成を突きつけられた。2001年1月にプライマリーバランス黒字化を達成したが、暮れに財政破綻した。
・ギリシャは、2008年世界金融危機の打撃を受けてIMFに融資を依頼したところ、アルゼンチンと同じようにプライマリーバランス黒字化目標を押し付けられた。2013年、目標を達成したが、代償としてGDPの1/4が吹っ飛び、失業率は26%になってしまった。2015年、事実上の財政破綻となった。
・財政健全化は、歳出削減や増税をしても、達成出来ないのである。これはなぜか?
国内民間部門の収支+国内政府部門の収支+海外部門の収支=0
この式から明らかなように、政府が赤字を減少しようとすると、民間部門もしくは海外部門の赤字が増大するのである。
・80年代後半、日本の財政赤字は減少し続け、90年には黒字に転じた。民間部門を見ると、黒字は減少し続けて赤字になったのである。90年代後半、デフレに突入し、民間部門は債務を減らし、債権を増やすようになる。逆に政府は、債務が累積するようになったのである。政府部門の黒字化は、民間部門の過剰債務、バブル発生の裏返しなのである。すなわち財政健全化は、バブルといった民間経済の不健全化なのである。当然バブル崩壊後、民間部門が債務を減らしたので、その裏返しで政府の債務が増えたのである。
・財政健全化をするには、政府は消費税の税率を上げられる。しかし、税率をあげても税収を上げることは出来ない。政府の税収は、経済全体の景気動向に大きく左右されるからである。また、政府は財政支出を削減することが出来る。しかし、税収が減れば財政収支は改善しないのである。結局、財務省がいくら頑張って増税や最終削減をやっても、財政健全化をしようとしたところで徒労に終わるだけなのである。
・日本は、財政健全化を目指す必要はない。むしろ、デフレなので財政健全化を目指してはいけないのである。財政健全化を目指して歳出削減や増税をしてしまうと、景気が悪くなり、税収の元である国民所得が減るので、税収が減り、財政健全化は達成されないのである。さらにまた、財政健全化を進める。平成日本はまさにこの無限ループを行なっていたのである。
デフレを脱却すれば、財政は健全化する。健全化したければ、財政赤字を拡大しなければならない。“財政悪化なくして、財政再建なし”である。財政健全化ではなく、国民経済健全化を図るべきである。
●感想
平成日本がいかに間違った政策を行ってきたのか目からウロコでした。
デフレ下とインフレ下で政府のとるべき対応は全く違うんだということを改めて気付かされたと同時になぜこうなってしまったのかと変わらない政府の対応を知ったことで苛立ちとやるせなさを感じました。多数派の方にいることはとても楽ですが、一方で間違った意見や思想もまかり通ってしまう危険性があります。この負の連鎖をとめるためには、正しいことを主張し続けて周囲を納得ることを継続するという地道で愚直な方法をとり続ける意外に道はありません。
私自身も今まで経済について全く知識がなかったのですが、これからも正しい経済学について学び続けていきたいと思います。
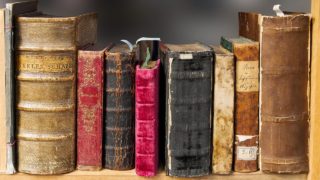



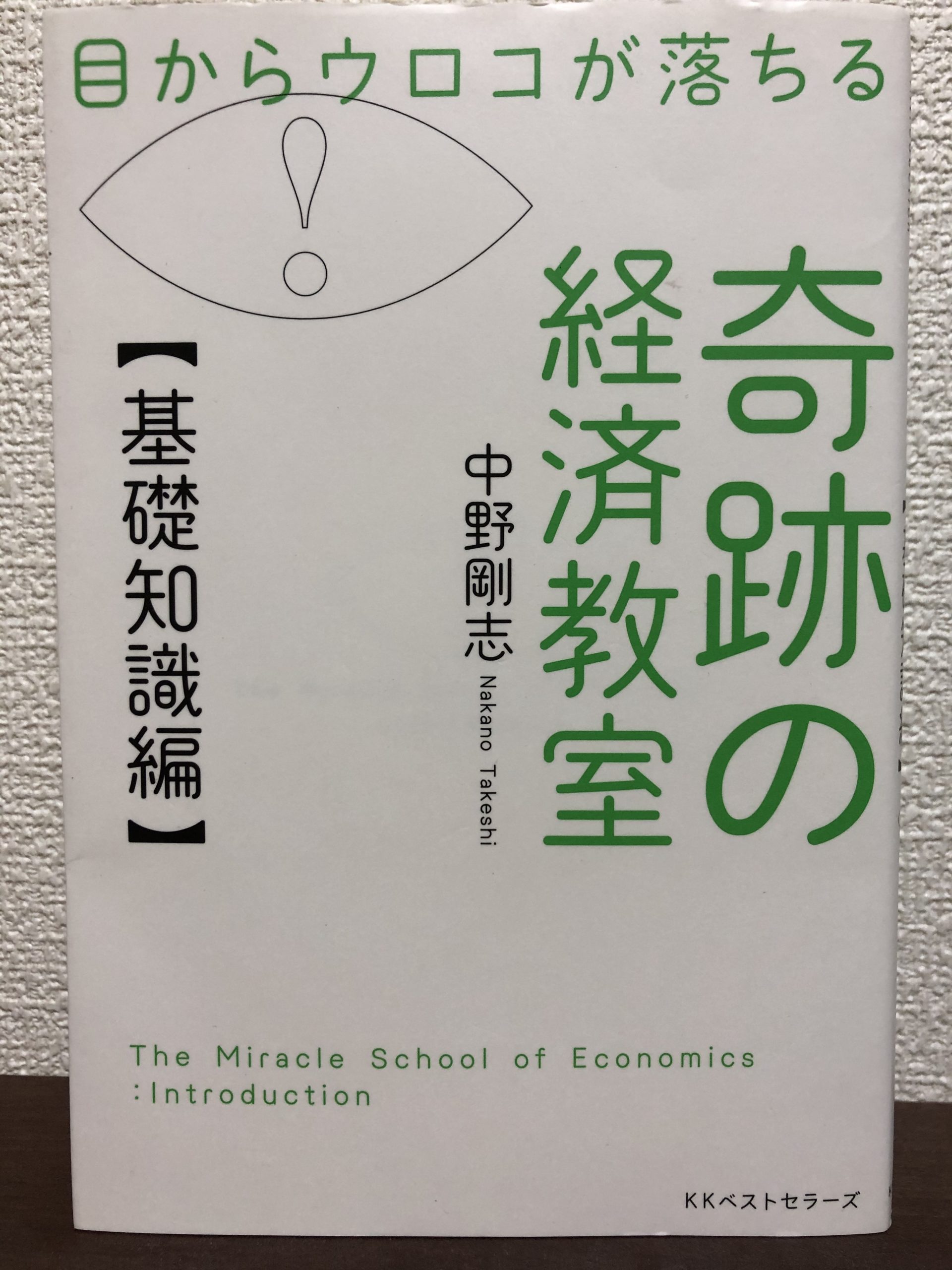
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1e22866f.0c6a6f3b.1e228670.899fd6df/?me_id=1213310&item_id=19539727&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F8953%2F9784584138953.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)